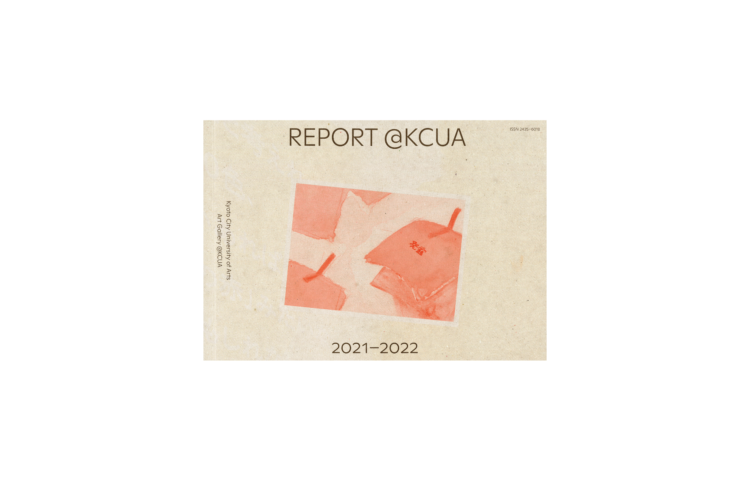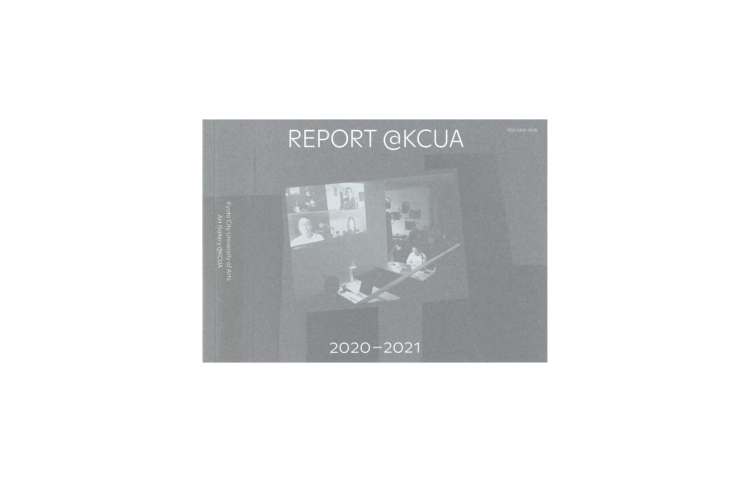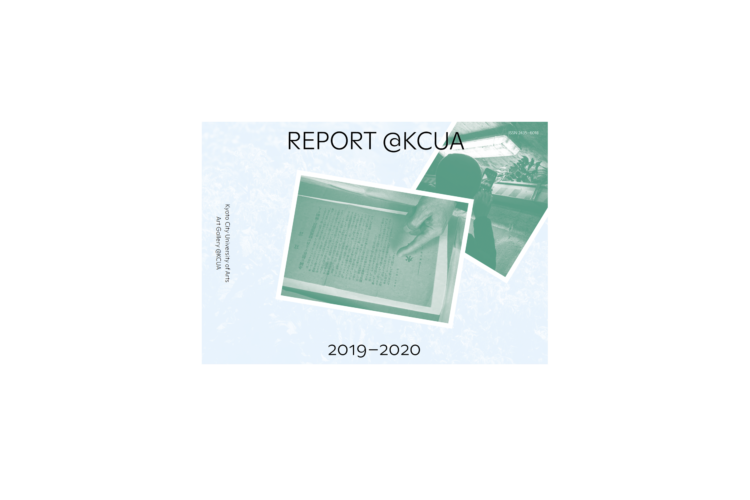Mission Statement
@KCUAとは
@KCUAとは
「@KCUA」とは、京都市立芸術大学の英語表記 「Kyoto City University of Arts」 の頭文字に場所(サイト)を示す「@」を付け、「アクア(ラテン語で「水」)」という読みをあてたものです。生命を養う水のように、芸術が人々の暮らしに浸透し、創造力豊かな社会に貢献するという本学の理念を表現しています。2010年にキャンパス外のサテライト施設として開設されましたが、2023年10月の京都駅東部エリアへの大学キャンパス移転にともない、キャンパス内施設として新たなスタートを切りました。
@KCUAでは当ギャラリー学芸スタッフの企画による「特別展」のほか、教員・在学生・卒業生を対象とした企画公募による「申請展」などの展覧会を開催しています。そのほか、国内外で活躍するアーティストを講師に迎えた若手アーティスト対象のワークショップやレクチャー、アートプロジェクトの実施など、展覧会だけにとどまらず、多岐にわたる活動を実施しています。
@KCUAに期待される役割には、以下の3つがあります。
- 1. 教育・研究成果を広く市民へ公開すること
- 創立以来140年にわたって本学では、様々な成果を生み蓄積し、大学の内外で公表しています。京都市の中心部に発表の場ができたことによって、より身近な場で市民に公開できる機会が得られることになりました。ここでは在校生、教員および卒業生の研究成果に基づく展覧会、ワークショップ、講演・講座等を市民向けに開催すると共に、京都を中心とする産業界や教育機関、研究機関との連携プロジェクトの成果を発表することが期待されます。
- 2. 芸術文化創出の人材交流の場とすること
- @KCUAにおける展覧会、ワークショップ、講座等の企画に際し、成果の公表そのものを目的とするだけではなく、学内、同窓会、市民、産業界、教育関係諸機関、研究所などとの連携プロジェクトを通じて、広く人々が交流できる場を形成します。
- 3. 芸術資源の連携活用の機能を果たすこと
- 本学と市民、京都市、産業界、他の諸機関が連携するにしても、基盤となるのは、情報の収集と交換です。京都が有する芸術資源としての人、物、場所、風景や景観、技術、材料、暮しの知恵に関わる情報を収集し、蓄積し、交流させる機関が必要となります。@KCUAは、その機能の一翼を担っています。
-

Photos by Takeru Koroda -

-

Staff
スタッフ紹介
スタッフ紹介

@KCUA長(工芸科漆工専攻教授)栗本夏樹
漆造形作家。「いのちの再生」をテーマに作品を制作。石や流木などの自然物や、車のボンネット、紙管などさまざまなものに漆を施し、新たな命を生み出している。学生時代はGMG(芸大ミュージカルグループ)の初期メンバーとして活躍。『オズの魔法使い』ではオズ役を演じた。

チーフキュレーター/プログラムディレクター藤田瑞穂
同時代を生きるアーティストや多様な分野の専門家と協働し、領域横断的な展覧会やプロジェクトなど、さまざまな「場」をつくる活動を行う。近年は特に、マルチスピーシーズをテーマとした芸術実践に強い関心を寄せている。基本的にオタク気質。2022年末に家族に迎えた愛犬を溺愛している。
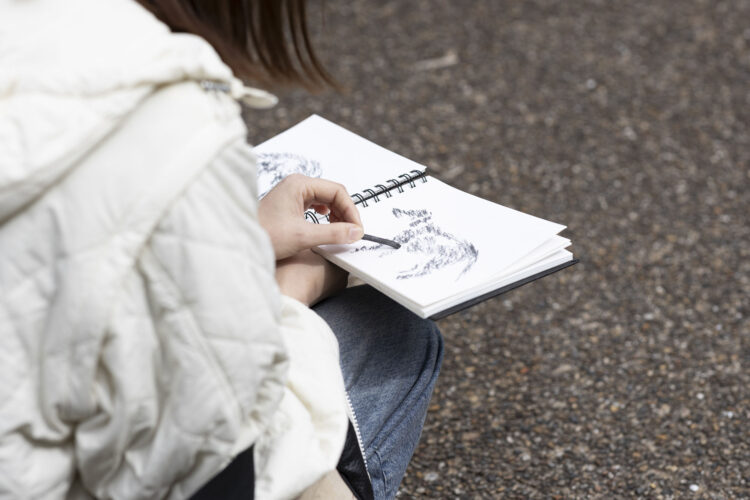
学芸員瀬田美晴

学芸業務補助・事務山本夏綺
ボランティアコーディネート、広報、「TOPOS:まなびあう庭としての芸術大学」の事業コーディネートを主に担当。作家としての活動では、日常にあるモノ(ストロー、おとし穴、クッキーなど)をモチーフにした作品の制作と、ワークショップを行う。管派/穴派、コーヒー派。

学芸業務補助・事務吉本和樹
Annual Reports
年次報告書