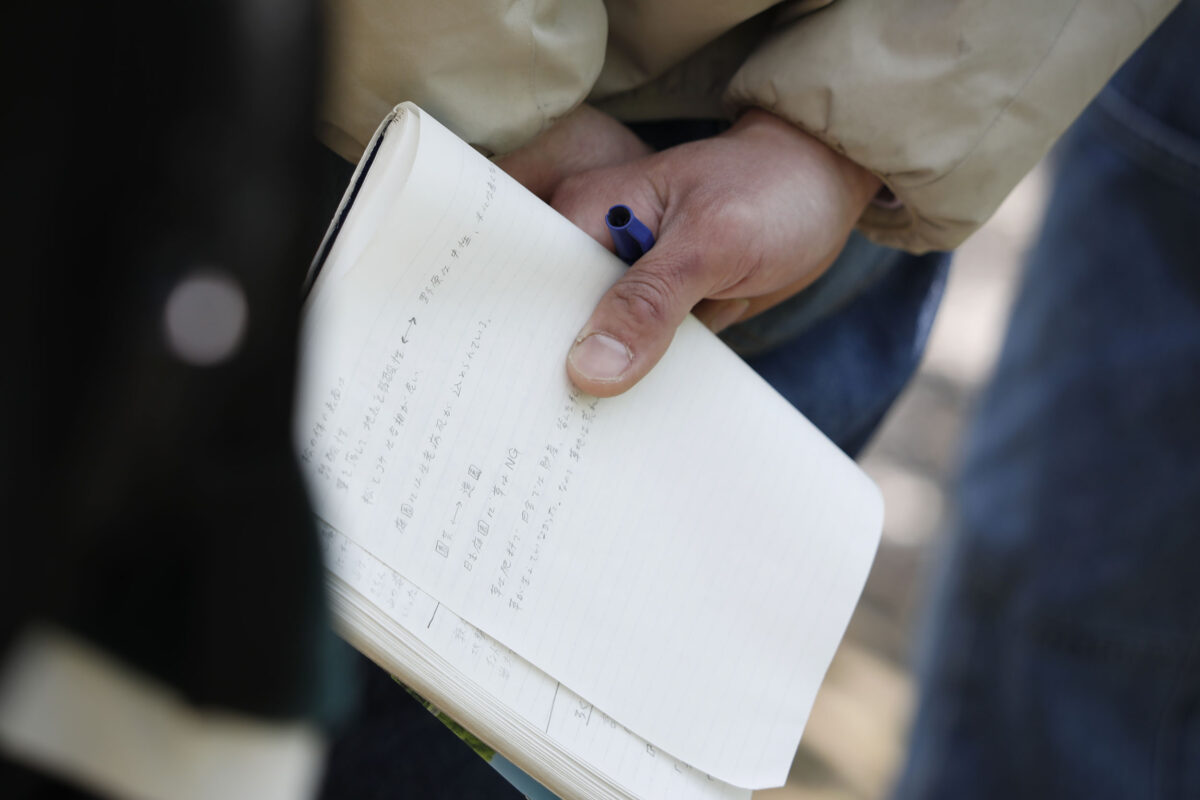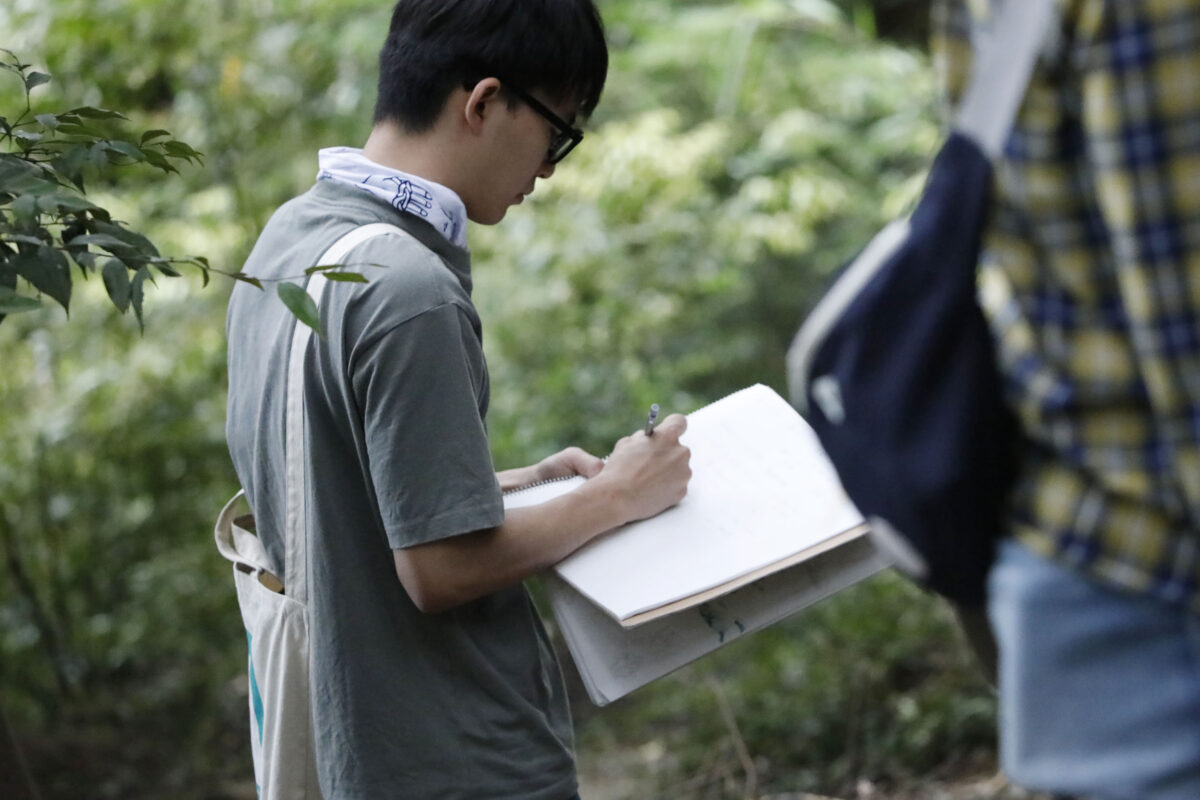PROJECTS
TOPOS:まなびあう庭としての芸術大学
プログラムA「生物多様性──人間以上/多元世界」

プログラムA「生物多様性──人間以上/多元世界」では、生物多様性をテーマにヒューマンスケールを超えた長期的な活動に携わる講師陣によるレクチャーならびにワークショップを通して、視野を広く持ち、物事を多角的に捉える技術を身につけることを目標とします。自分の普段の活動とは異なる専門分野の実践者・研究者とのコラボレーションのあり方を学びます。
① レクチャー・フィールドワーク@渉成園
日時:2025年4月26日(土)9:00–12:00
会場:渉成園
講師:太田陽介・鷲田悟志(庭園ディレクター・職人/植彌加藤造園株式会社)
モデレーター:安藤隆一郎(京都市立芸術大学美術学部染織専攻准教授)
藤田瑞穂(@KCUAチーフキュレーター/プログラムディレクター)
太田陽介さんと鷲田悟志さんの仕事である渉成園の庭づくりについて、その背景にある歴史や思想を踏まえながらお話しを伺いました。植物同士の共生や昆虫・鳥との関係性なども組み込まれた庭づくりの実践から、「生物多様性」について新たな視点を得る機会となりました。
太田陽介(おおた・ようすけ)
庭園ディレクター/職人。御用達として東本願寺・渉成園の担当を務める。渉成園内に息づく生物多様性を守るため、創意工夫を凝らしながら育成管理に励む傍らで、京都の景色に欠かせない東山の林相改善事業の整備や研究にも勤しむ。いきもの全般に愛着を持ち、生物の視点から庭を見ることに重きを置いて渉成園に携わる。自然界にあるものは「とりあえず何でも食べてみる」主義。
鷲田悟志(わしだ・さとし)
庭園ディレクター/職人。御用達として東本願寺・渉成園の担当を務める。理性を超えた芸術作品としての日本庭園の魅力に惹かれ、庭づくりに携わる職人。学びを深めた現代美術をバックボーンに、日本庭園と芸術・文人文化をより密につなげていくことを目標として日々の手入れに勤しむ。
参加者のコメント(抜粋)
私は医療などの視点から、観察される対象の多様性ではなく、観察する主体側「わたし」の多様性に興味があります。そういった「臨床的」視点から見ますと、十百千万~年といった時間変化を感じさせる今回の視点は、その対極の「科学的」視点であったはずなのですが、対極といった感覚がなく、ここにも主体側の「わたし」の多様性や自由(おのずからによる)を強く感じました。世の中の価値観が大きく変わろうとしている今、「庭」を一つのきっかけとして思考的ではなく、実感的に身体で語り合っていく場がとても貴重ですね!!
現場で実践する者としての、理論的な学者の方との考え方の齟齬や葛藤もあるとお聞き受けしましたが、今後世の中の流れに伴い、渉成園のような動きが増えていくことに私個人としては希望を感じます。
私は染織を専攻していますが、繊維業界でも人手不足や産業の衰退が叫ばれて久しい中、工場が請負の仕事だけではなく自社ブランドを立ち上げたり、農業や音楽などとも緩やかな繋がりを持ち地場を盛り上げていくような動き(播州のtamaki niime、富士吉田のハタオリマチフェスなど)があり、地域性・多様性・共創などというテーマはどの分野においても共通のキーワードなのだなと思います。
自分は子供の頃から生き物や自然が好きだったのですが、まだまだ知らないことが多いと学べた貴重な機会になりました。これからも山を登ったり散歩するとき、植物や生き物を見かけたらその背後にあるものや生えている意味に思いをはせながら自然を楽しみたいと思います。
講師への質問と回答
Q:
今回紹介された庭園の管理手法や思想は、都市部や異なる気候・文化圏でどう応用可能か。また、職人として長期的に自然と向き合う中で、大きな環境変化(気候変動など)の対応や考え方について、もう少し詳しく伺ってみたいと思いました。
A:
渉成園の管理手法や哲学は、異なる国、環境でも応用出来ます。渉成園は真宗大谷派の庭園ですので、その思想を反映させた管理方針という意味で「真宗式庭園」と名付けて管理をしております。その土地の環境や宗教、哲学、社会問題などを組みした形で管理をしていくスタイルなので、「真宗式庭園」ではなく、別の場所ではまた少し違った名前がつくのだと思います。
気候変動に対応した形の手入れを行っていますが、同時に気候変動に対応するには限界があるとも思っております。いくら我々が必死に護ろうとしても間に合わない場合があります。痛感したのは 2018年9月4日の台風21号です。浸雪橋のたもとに生えていた大きなタイワンフウの木がカキノキ諸共倒伏してしまい、大きな被害をうけることになりました。しかし、一つの命が終わるということは、次の命に場を譲るということでもあることにその時気づかされました。現在タイワンフウの生えていた場所には小さなモッコクの木が生えており、カキノキは主軸が折れたものの、萌芽更新という形で少しずつ大きく成長しています。(柿8年ならばもう少しでまた実をつけるはず)環境の変化からくる反応をしっかりと観察し、コントロールは仕切れないことを前提に対処していくといった感じでしょうか。この地球に暮らす一個体として、他の命をモノの様に扱わないように心がけております。(太田陽介)
Q:
日本庭園ではこのような取り組みをしているところはなかなかないとのことでしたが、ジル・クレマンの思想や多様性を軸に作られている庭や公園がどこかにあれは教えていただきたいです。
A:
ジル・クレマンの思想を元に造られた庭は多数あります。
・アンリ・マティス公園:フランス北部の都市リールに位置する公園で、クレマンが全体を設計し、1990年から1995年にかけてつくられました。
・レイヨルの領地:プロヴァンスの地中海沿岸にある庭園で、1989年から始まったプロジェクトです。クレマンが手がけた公共の庭としては初期のもので、地中海性気候区に属する世界各地の植物が植えられています。
・クレマンの自庭:フランス中央部のクルーズにある彼自身の庭で、「動いている庭」の原型とされています。植物の動きを観察し、自然の営みを重視する彼の思想が色濃く表れています。
・アンドレ・シトロエン公園やケ・ブランリー美術館の庭:パリにあるこれらの庭園も、ジル・クレマンが手がけたことで知られています。
日本庭園で言うと東京都の六義園、名古屋市の白鳥庭園では生物多様性に配慮した管理が成されているようです。我々もまだ行ったことが無く、視察が必要だと考えております。また、多様性を軸にと言いますとクレマンの庭はもちろん、兼六園や後楽園、偕楽園などの日本の回遊式庭園は歩きながら景色が変化していくという意味で言うと多様です。(太田陽介)
Q:
印月池で説明を受けていた時、池を挟んだ向こう側にあえて外来種を受け入れた場所を用意しているとおっしゃっておられたと思います。気になったのが、あの時奥から聞こえていたカエルの鳴き声もしていて、京都市内では珍しいように思いました。あのカエルたちも、あえて飼育しているのでしょうか。
A:
残念ながら現在渉成園にはカエルがおりません。アオダイショウやシマヘビなどの捕食者は多いのですが……。しかしウシガエルなど外来のものが入っていないだけマシなのかもしれません。池の奥から聞こえたとのことでしたので、もしかするとアオサギの声かもしれません。飛んでいる時は「ギャア!」と鳴くのですが、巣にいるときは「クヮクヮクヮクヮクヮ」と鳴いてます。飼育は基本的にしません。カエルがいたとしても、アオサギがいても積極的に保護も基本的にはしません。ただ、関係性の中で居てくれるということが重要だと思っています。希少種などはその関係性の中で成立するような最低限のテコ入れを行うこともあります。(太田陽介)
Q:
太田さんのお話に出てくる生物に対するリスペクトを込めたアプローチの源泉は幼少期からの興味関心やご経験によるところが大きいでしょうか。それとも庭師さんのお仕事に就かれて一から学び直されたのでしょうか。
A:
私の生物リスペクトの一番の根源は幼稚園時代だと思っております。私は永観堂幼稚園に通っていたのですが、園内の運動場の片隅にお墓がありまして、その横に梅干し用(?)の焼き物の壺が置いてあります。その壺に園内に落ちている昆虫の死骸を入れて手を合わせるという緩い決まりがあったのです。意味もわからずひたすらやっていましたが、その後の人生で自分が昆虫などの動物を殺める度にその記憶を思いだしていました。それはやがて「生きているとは何なのか?」という疑問に置き換わり、それが今は私の人生のテーマにもなっています。大学時代はずっと様々な生物の生態を学ぶ傍ら、生命の根源的な存在である細菌の研究に打ち込みました。しかし、そこからのアプローチにも限界を感じ、自分の生活を立てる為に始めたこの仕事からそのヒントを探っている日々です。(太田陽介)
Q:
今までお茶の木を使った庭園は宇治ぐらいでしかあまり見たことがなく、最後の集合場所の裏手に茶の木を植えた庭園があって驚きました。お茶に限らず、実際に庭園で植えたものを摘んで食べるという庭園も存在するのでしょうか?
A:
庭園に植えられたものを食べるというのはあります。水戸の偕楽園では現在も「梅の実落とし」と言って、収穫された梅を一般向けに販売しております。和歌山の大名庭園である養翠園も現在はクロマツばかりになっていますが、かつては柚園が一部あったこともあり、主食とまではなりませんが、何か有事の際にも利用できる様な植物が植えられている例は多々あります。(太田陽介)

② レクチャー・フィールドワーク@東山地域
日時:2025年5月24日(土)9:00–12:00
会場:東山地域
講師:髙田研一(髙田森林緑地研究所所長/ NPO 法人森林再生支援センター常務理事)、太田陽介・鷲田悟志(庭園ディレクター・職人/植彌加藤造園株式会社)
モデレーター:安藤隆一郎(京都市立芸術大学美術学部染織専攻准教授)
藤田瑞穂(@KCUAチーフキュレーター/プログラムディレクター)
東山地域の山の中で時折立ち止まり、講師たちの山づくりに関するお話に耳を傾けました。その場所に存在するさまざまな境界について、歩いたり、感じたりしながら体感できるフィールドワークとなりました。
髙田研一(たかだ・けんいち)
生態学者。自然環境をめぐる諸分野を統合的に考えようとしている専門家で植える木も、働く人々も、そこの場も生かすための「自然配植」の提案者。山地・森林評価技術、育成技術等の提案。とくに、これまで設計という概念のなかった林業分野で、設計という概念の導入を行い、三種の主たる公益性評価に基づく森林育成をシステム化し、各地で実施してきた。(単純肉体労働から、面白くやりがいのある知的肉体労働への転換)近年では、重機などの進入が困難な山林の斜面崩壊、土壌侵食防止する目的で使用される「小土木」(KODOBOKU)を提案している。現在、NPO法人森林再生支援センター常務理事、奈良県フォレスターアカデミー特任教授等を務める。昭和25年11月、京都市生まれ。
参加者のコメント(抜粋)
京都という都市は、まさにこの三種の山が重層的に存在し、それらと共に形成された多様な信仰・生活・景観文化が現在に至るまで継承されています。そのような場で行われたフィールドワークは、「自然」や「文化」を分けて捉えるのではなく、相互に影響しあうひとつの動的な生態系として理解することの重要性を、理論ではなく実感として気づかせてくれました。
また、フィールドワーク中とても印象的だったのが、「我々は時代に逆行してでも、植える木も、働く人々も、そこの場も生かす自然配植を行う」というお話です。低コスト低リターンが主流である今の日本の資本主義社会にはとらわれない自然配植がなされていて、3人の熱い想いと信念が伝わってきました。
感想だけでは言いきれませんが、有意義で、学びの多い時間を過ごすことができて良かったです。この度はこのようなご縁をいただきありがとうございました。
高田先生は、清水寺の水脈の話をしてくれました。高田先生は、目先の経済利益に惑わされず物事の本質が何かということを山を通してお話をされました。その目先の利益に惑わされないことが未来の人たちの生活を現在の私たちが守ることになると受けとめさせてもらいました。
とても貴重な体験でした。お世話になりました。ありがとうございました!
講師への質問と回答
Q:
髙田さんからは山づくりにおける精神面を、太田さんと鷲田さんからは山づくりにおける技術面を教えていただきました。植彌加藤造園株式会社の職人であるお二人に、精神面をどの程度重視されているのかお聞きしたいです。
A:
山づくりにおける精神面は山づくりの方法と同様に大切だと思っております。技術という言葉がありますが、ただの方法論であってはいけないと思っています。ただの技ならば方法と言い換えることもできるでしょうが。私は技術の術は祈り、願い、念の様な何か精神的なものを含んでいると解釈しております。枯れかけた一本の木を守りたい。というたった一つの願いや祈りから技術は生まれるのだと思います。その思い無しに機械的に「こうやればこうなる」だけでは良いものは出来ないと実感しております。技だけでもダメ。術だけでもダメなのではないでしょうか。(太田陽介)
私の場合「精神」は、なかなか普段使わない言葉なので、例えば「日本庭園の精神」どこに存在しますか、などと言われると、「やっかいだなー、」と思ってしまいます。そう考えてみると、精神面を特に重視してないのかもしれません。
コンテキストをかなり重視しております。
現代において「日本庭園」を造るなんて違和感しかない行為です。「一体全体、なぜ?」って思います。まったく当たり前ではない。既存の庭を修復、維持管理したりする際でも、何も考えずにはも進めない。
庭は常に気候、風土、施主、社会状況、同時代性にさらされております。庭師の仕事はそれらの間を取り持ち、調整すること、再接続すること。その都度、先人の方法を参照しながら、考えながら実践を重ねていく。それが庭における技術だと考えております。(鷲田悟志)
Q:
「神の山・仏の山・農耕の山」という三分類は、地質的条件と人間の文化的実践の連関を見事に言語化したフレームだと感じましたが、この分類はあくまで京都という特殊な都市構造や歴史的背景をもつ地域に固有のものなのでしょうか? それとも、日本の他地域、あるいは東アジア文化圏全体に通用するような比較文化的・比較地理的な適用も可能でしょうか?また、近代以降の土木技術の発達や都市化の進展によって、これらの山の機能や意味が変質してきた事例があれば伺いたいです。特に、かつて「神の山」や「仏の山」として信仰・死生観の拠り所となっていた場所が、現在どのように都市の中に再編成され、あるいは忘却されていっているのかといった、文化的遷移のプロセスに関心があります。
A:
「神の山・仏の山・百姓山」は京都固有のものではないと思います。山が単なる地形ではなく、信仰の対象(神の山・仏の山)や生業の場(百姓山)として認識されるという点は、山岳信仰や里山利用が見られる多くの文化圏で普遍的に見られる現象ではないでしょうか。例えば信仰対象、資源供給源、交通路としての山など、信仰や生業といった視点から分類する試みは、地域を超えて有効だと考えられます。
東アジア文化圏で考えてみると、中国の五岳信仰や朝鮮半島の山岳信仰、ベトナムの山岳民族の文化など、山が精神的な意味を持つ例が多く見られます。また、棚田や焼畑に代表されるように、山地での農耕も広く行われています。
これらの山の機能や意味が変質してきた事例は、燃料革命や都市化が代表的な事例だと思います。山と生業が全く結びつかなくなり始めてから信仰が薄れていったのではないでしょうか?山の神様に祈る必要がなくなるのです。かつての神の山や百姓山は観光地としての山、レクリエーションの場としての山になっている場合があります。一方、神の山は現代ではパワースポットという形に置き換わる形で残っている場所も多く見られます。しかし、高度経済成長期から都市化されていく中で山に暮らす人々のコミュニティーが衰退し、祭りや行事が存続できずに忘却されていく事例は現在進行形であります。(廃村など)山に道路がひかれた場合はリゾート開発や宅地開発なども行われました。バブル期の負の遺産としてゴーストタウンになっている場所もあります。
これらの変質は、近代化、都市化、グローバル化といった大きな社会変動の中で、山と人間との関係性が再定義されてきたプロセスを如実に示しています。かつての「神の山」や「仏の山」が都市の中に再編成される過程では、その歴史的・文化的な意味が薄れたり、新たな意味が付与されたりする一方で、完全に「忘却」される場所も少なくありません。このような文化的遷移のプロセスを多角的に捉え、未来に向けて山の価値をどのように継承し、再構築していくかが、現代社会における重要な課題であると言えるでしょう。(太田陽介)
Q:
太田さんが作られた道の側に剥がれた木の皮が山状に積まれている様子は、降雪地帯の「雪よせ」の景色と少し似ていて面白いなと思いました。小枝や木の皮を集めて置く場所はなにか意識的に決められているのでしょうか?感覚的に「道にはしない」と思った場所においているのか、あるいは地面を保護するためにおいているのかなど、理由があればお聞きしたいです。
A:
我々が行っている森づくりでは主にコジイ、ヒノキ劣勢木などの常緑樹を伐採対象としています。伐採された樹木達は搬出することはありません。社会として木材が必要とされておらず、パルプ材の原材料として搬出するにしてもとてもコスト面で採算がとれません。ですので、基本は現地に残置することになるのですが、その置き方には工夫が必要です。
基本的にはゴミをためて崩れ落ちる場所に置くことは出来ません。枝葉は安定した角度の斜面、既存樹木の根本に引っ掛ける様に置いたりします。幹は斜面下に転げ落ちない様に玉切りはできるだけしません。枝を幹側に長い目に残して切ること、幹を細断しないことで、急斜面でも転がる事無く安定して置くことが出来ます。安定した幹には枝葉ゴミを貯めることも可能です。よって、伐採して木を倒す時にはどの方向に倒すのかが重要になります。既存樹の根本にゴミをためる時は、分解される過程で出てくる腐植による影響を受けないかどうかを考える必要があります。例えば腐植を嫌うアカマツやヒノキの株元にゴミをためることは基本的にしません。そして、見た目も重要になります。例えば、今回作った道以外にも既存の管理道がありました。そこから見た時に見えすぎること、違和感は無いかなど考えた上でゴミをためております。
さて、本題の木の皮をなぜあの場所に置いたのかです。そもそもあの場所に枝葉ゴミをためておりました。その枝葉ゴミをヒノキの皮を敷き詰めて隠したのが一つ。そして鳥居の場所は今回作った道の中でも一番急登している箇所であり、鳥居を作る為のワークスペースが限られていたこともあります。あの皮を敷き詰めていた場所は枝葉ゴミがあることで地形が平になり、鳥居作りには最適な環境でもあったのです。
そうやって各所にためられたゴミは最終的には放線菌、きのこ、カビ類を経て分解されていきます。そういった生物の助けを得やすいように枝葉と菌類の付いた落葉や朽木を途中で混ぜたりしております。
今回山道を作った場所は5年前からコジイやヒノキ劣勢木を伐採し出しました。ゴミの集積場所は上記の様な工夫をしながら決定してきました。この集積されたゴミが今回山道を作ると決まった時に、問題になるだろうと予測されてました。道を通す為にゴミを移動させる仕事が大変だと思っていたのですが、予測は外れ、ほとんどゴミを移動させる事無く今回の道づくりを終えました。なぜなのか。色々考えていたのですが、ゴミの置く場所を選定する時に、人目に付きにくい場所を選んでいること、神籬の様な一本で魅せられる様な立派な木の根元にはゴミを絶対ためないこと、などが関係していると思われます。そもそもゴミをためているような場所は元々魅力が薄いような場所を選んでいたのだと実感しました。鳥居を作った場所の横にゴミをためていたのは、元々一番きつい急斜面でウラジロというシダ類が強烈に繁茂している場所でヒトが立ち入れる様な環境では無かったことに起因しております。急斜面のウラジロの森を切り開き、そこに枝葉をためて、急斜面地に平場を作ること、さらにその枝葉をウラジロに覆いかぶせることによって枯らすことも目的の一つでした。森づくりにおいて、伐採した木を搬出しない場合、美しく魅せることに一番苦労しております。枝葉ゴミを置く場所について興味を持って頂いたこと。とても良い着眼点だと思います。(太田陽介)

③レクチャー #1
日時:2025年7月13日(日)13:00–15:00
講師:伊勢武史(京都大学フィールド科学教育研究センター准教授)
モデレーター:藤田瑞穂(@KCUAチーフキュレーター/プログラムディレクター)
「人はなぜ自然を愛するのだろう?」というタイトルのもと、進化生物学の視点から見た生物多様性や人間の存在についてをテーマとしたレクチャーを実施しました。「美」とは何か、なぜ人間は美的感覚を持つのかなどの問いについて、生物学者の立場ではどのように考えるのか、参加者からの質疑応答を交えながら丁寧にお話しいただきました。
伊勢武史(いせ・たけし)
京都大学フィールド科学教育研究センター准教授。ハーバード大学大学院修了(Ph.D. in Biology)。独立行政法人海洋研究開発機構特任研究員、兵庫県立大学シミュレーション学研究科准教授を経て、2014年より現職。専門は森林生態学・環境科学。人間と自然の持続可能なつきあい方について、シミュレーションや人工知能など情報科学技術を用いた研究を実施している。同時に、「人間とはなにか」という問いの答えを求めて、進化心理学にもとづく実験も継続している。サイエンスコミュニケーションがライフワークであり、著書に「学んでみると生態学はおもしろい」「生物進化とはなにか」「生態学は環境問題を解決できるか」「生態学者の目のツケドコロ」「2050年の地球を予測する」などがある。2025年度から中学国語の教科書(光村図書・東京書籍)に著作が掲載されることに。
参加者のコメント(抜粋)
一方で、今の社会はその本能を忘れてしまうほど自然と人間の関係性が希薄になっており、自然を求める行動自体が自然資本の消費を助長する傾向も感じます。自然も人間も幸せになるためには学習が欠かせないと思います。学習も、意識の高いものでなく、クリエィティブな人だけでもなく、普通の人の内発的な動機付けを喚起できるか。そこにアートの力が活かせればと思いました。
講師への質問と回答
Q:
地球温暖化が益々厳しくなっていく地球上において、人類がそれに適応するという意味で進化するとしたら、生物学の視点からはどのような進化が考えられるでしょうか。
A:
進化についてよくある誤解は、「人類はこうあるべき」という将来像を語ることと、生物進化との混同です。よって以下の回答は、あなたの期待に沿っていないかもしれませんが、生物学者の見解をお伝えします。
進化が起こるには、人の持つ特徴が原因となって子孫の数に違いが現れることが不可欠です。温暖化によって特定の人々が少子化する/多産化する、温暖化によって特定の人々が早死にするようになる、などの変化が現れれば進化が生じる可能性があります。ただし、現時点では、そのようなことを考える合理的な理由はありません。
Q:
27クラブなど、業績を残した上で若くして死ぬことが伝説化(≒美化)されることがあります。これは進化心理学的にどのように考えることができるか、お聞きしてみたいです。
A:
時間がなくて触れられなかったのですが、人間は社会生活を営むために自己犠牲などが必要になることがあり、文化としてそれを賞揚することで社会を維持することがあります。命をなげうって人を救った英雄などは、世界のさまざまな民族で語り継がれ模範になりますね。これは、集団でいなければ子育てがむずかしい人間という生物の特徴が現れたものだと考えられます。
Related Pages
関連ページ