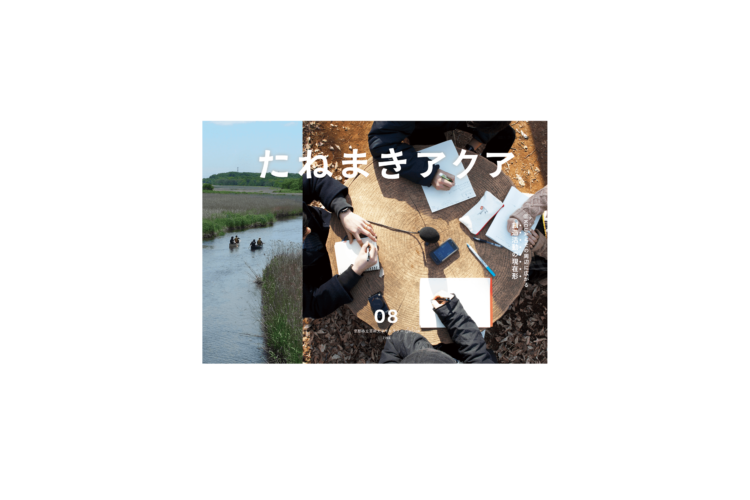INTERVIEW @KCUA
たねまきアクア 08
チェン・ティエンジュオ インタビュー
聞き手:ジュリエット・礼子・ナップ(KYOTO EXPERIMENT 共同ディレクター)、岸本光大(京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA 学芸員)


パフォーマンスから映像、デザイン、ファッション、電子音楽、宗教まで、ジャンルやメディアを自由に横断する中国ミレニアル世代の旗手、チェン・ティエンジュオ。京都市立芸術大学ギャラリー@KCUAでの日本初個展では、キッチュでクイア、そして恍惚に満ちた作品世界にどっぷり浸かることのできる贅沢な空間が広がります。その発想の根源に迫るべく、展覧会の中心となる最新作《The Dust》や制作のテーマ、チェンのプロデュースによるライブパフォーマンスイベントまで、話題たっぷりなオンライン・インタビューの様子をお届けします!
上画像:
チェン・ティエンジュオ「牧羊人」ライブ・パフォーマンス(2021年10月3日)
撮影:前谷開、提供:KYOTO EXPERIMENT

─新型コロナウイルスの世界的な感染拡大は未だ世界に大きな影響を及ぼし続けています。来日が叶わず、当初の計画から変更を余儀なくされて、遠隔で準備を進めることになってしまいましたね。昨年からずっとこんな感じだと思うのですが、このパンデミックはチェンさんの活動にどのような変化を及ぼしましたか?
このパンデミックが始まった頃、僕は世界全体が崩壊していくような気持ちになっていました。「全世界共通」という考え方が崩れて、ナショナリズムが盛り上がってきてしまってて。みんな自分の健康や国のことばかり気にしているし。そんな中で家に閉じこもって過ごしていたら、どんどん憂鬱な気持ちになりますよね。やっと家から出られる、っていう頃には、もしかしたらこんなヤバい感じがもはや普通になっちゃってるんじゃないか、とか考えたりしませんでしたか?
それで僕は、人間の出てこない作品を作ろうと思いつきました。パンデミックで人類の終焉が近づいている、みたいな悲壮な雰囲気になっていても、ウイルスからしたら、ただ生き延びようとしてるだけなんですよね。この地球上に共存している種のうちの一つとして。それが今回の展示の中心となる映像作品《The Dust》のアイデアにつながっていきました。動物や他の生き物、かつて人間が作った彫刻だけが存在する世界と、そこで始まる物語です。
あらゆる彫刻や楽器とかって、元はと言えば人間が生み出したものですけど、長い長い年月を経ると、自立した存在になると思っていて。人間が最初に与えた意味を受け継ぐだけでなく、独自の歴史と意味も持っている。つまり、別の何かというか、なんて言ったらいいのかな……とにかく独自の性質を持つものになるんです。風葬の跡に遺された頭蓋骨や骸骨も同じような感じですね。そういった、人間の遺物についての作品を作りたかったんです。
あと、自宅のスタジオで一人、絵を描き始めました。絵を描くっていう行為自体が楽しいし、まだ完成していなくても、あるいは満足のいくように描けなかったとしても、プロセスそのものが面白くて、やる気が出てくるんです。このパンデミックの2年間で、初心に戻ってきたような感じがしています。そうやって描いてきた絵はまだ展示したことがなくって、実はこの展覧会で初めて展示するんです。ずっと絵なんか描いてなかったんだし、映像あるじゃん、自信持って出せるものだけ出せよ、って感じかもしれないんですけど、いまやりたいのはそういう従来型のパーフェクトじゃなくて。個展なんだし、やりたいことをやるべきだよなって思ったんですよね。だから《The Dust》を展示するメインの展示室は、世界的なパンデミックが起きた後でできたものばかりで構成しました。部屋の片側には人間が登場することのない《The Dust》の映像とパフォーマンスがあって、もう片側には僕が孤独の中で描いた絵がある。それが、いまの僕が作るこの部屋の「パーフェクト」だって思っています。

─《The Dust》の部屋とは対照的に、他の3つの部屋に展示された作品には多くのパフォーマーが登場しますね。
他の部屋で展示されるのは、重要なパフォーマンス作品です。映像はパフォーマンスを全尺で記録しています。《TRANCE》(2019)はハンブルグにある劇場のカンプナーゲルから依頼されて制作したパフォーマンス作品なんですけど、パンデミックの影響でまだ上演できていないので、展示するのはリハーサルを兼ねて北京の個展で実施したデモ版のパフォーマンスの記録映像になります。《TRANCE》のパフォーマンスでは、パフォーマーの身体は最初から最後までの12時間、あまり装飾を施されず、人間としてのありのままの状態になっています。そして鑑賞者は、普通の人間がいかにしてトランス状態に変化するかを目の当たりにします。魂や精神がどのように身体から引き離され、変容していくのか。そして身体はただの抜け殻になってしまいます。そういう意味で、最終的には「人間」のいないパフォーマンスになるわけです。
また、超人や悪魔たちが登場する圧倒的で混沌とした《ISHVARA》(2016)やダークでアップビートなポップオペラの《An Atypical Brain Damage》(2017)も紹介します。それらの作品には全て、何らかの形で誕生から終焉までの物語を内在させています。これら3つが主な作品になります。
パフォーマンスを制作するときにはいつもたくさんの彫刻や平面作品を作っていて、舞台美術になるものもあれば、彫刻作品になるものもあります。それらのすべてを日本に持ってくることはできないので、パフォーマンスとの関連性が高いものや、作品の全体像の把握につながるものを選んで、映像と一緒に展示しています。

-
![]()
《ISHVARA》 -
![]()
《An Arypical Brain Damage》
それと、《Exo-Performance》(2019)のパフォーマンス映像もあります。これはアンドリュー・トーマス・フアンと一緒に行った小さなプロジェクトで、パフォーマーのモーションキャプチャーを活用して架空のCGIの風景を作って映像作品の中に取り入れました。
あともう一つ、インドで行ったストリートパフォーマンス《G.H.O.S.T.》(2017)も展示します。それまで、ギャラリーや劇場では多くのパフォーマンスを上演してきましたが、ストリートでもやった方が良いな、と思っていたんですよね。それで、インドで撮影しているときに、都市の中の自然であるガンジス川でパフォーマンスをすることを思いつきました。街や環境って、それ自体がすごく豊かだと思うんです。それにガンジス川って、ヒンドゥー教徒にとってはヒンドゥー文明が始まったと信じられている聖なる川ですしね。僕の作品は宗教や儀式と強くつながっているので、この作品を今回の展覧会で展示することは、自分の中で重要な意味を持っています。
今回の展覧会では、それぞれの作品が輪のようにつながっている感じなんで、部屋の順番に観てもらっても良いし、逆走しても良いし、好きな順番で鑑賞してもらって良いですよ。
─チベット仏教を信仰しておられますが、先ほどおっしゃった、宗教や儀式とご自身の制作活動について、詳しくお話しいただけますか?
仏教徒になったのは2012年です。友人や家族が亡くなっていくのを目の当たりにするうちに、死や別れが怖くなってきたんです。生きているということは、死への準備をすることでもありますよね。そういう自分の不安に対処するための何かが必要だと感じていたときに出会ったのが、チベット仏教でした。
それに、チベット仏教の豊かな歴史に惹かれたんです。チベットの絵画には、さまざまなレベルの輪廻転生、多様な神々の姿や仏教徒の姿が描かれているんですけど、これらの物語は、僕の作品のすべてにインスピレーションを与えてくれました。
それと同時に、ヒンドゥー教など他の宗教にも興味があります。ヒンドゥー教は、死や輪廻という考えをどのように扱うかという点で仏教と似ているし、互いに影響し合っていて、同じような物語を共有しています。なので、すごく気になるんですよね。
《The Dust》に登場する寺院は、僕が仏教徒になった場所なんです。だから、ここで作品を撮ったことで、仏教を信仰することになった個人的な歴史や記憶を辿るような作品になりました。一年に一度だけ行われる儀式の撮影もしました。村人がみんな集まって幸運を祈る、昔から続く儀式です。僧侶たちは皆、神の装いになって、仏陀や神像の物語を踊っていました。RPGゲームみたいな感じでもあり、いろんな登場人物が出てきて物語を語る、オペラのようでもありました。さまざまな楽器が演奏されていて、真ん中でダンスをするグループがいて。あのパフォーマンスは強烈でしたね。作品にその映像自体は出てこないんですけど、読経や儀式の音だけは使っています。


─展覧会のタイトル「牧羊人(ムーヤンレン)」はどのような意図で名付けられたのでしょうか?
2ヶ月ほど前、作物も育たないほどの高地にあるチベットの小さな村に3週間滞在し、小学校に通う子供たちにボランティアでアートを教える機会がありました。その村で暮らす人々のほとんどは遊牧民で、「牧羊人(中国語で“羊飼い”を意味する)」だったんです。それが直接的な名付けのきっかけなんですけど、なぜかって言うと、羊飼いって、仏教でもキリスト教でも、さまざまなものの例えになっているんですよね。例えば仏教だと、シッダールタは羊飼いの少年にヤギの乳を捧げられたことがきっかけとなって、悟りを開いて仏陀になったと言われています。僕の作品にはチベット仏教に関するものがいっぱいあるので、結構こういう例えに結びついていたりします。例えばパフォーマンス作品には、この羊飼いのような性質、つまり捧げものをする登場人物が常に出てきます。そうして作品によって形は違ったとしても、供養や犠牲の儀式が同じように行われるんです。また、羊飼いは、媒体のような性質も持っています。羊=失われた魂で、それを追うのが羊飼いっていう例えで。つまり何かを追うことでそれを別のものへと必ず変換するような、何かと何かをつなぐ存在だと思っています。
この展覧会では、最初のパフォーマンス《ISHVARA》から最新の映像作品《The Dust》までを紹介しているので、僕のアーティストとしての実践がどのように変化していったかを辿ることができます。そういう意味でも「牧羊人」というタイトルはこの展覧会にあっていると思うんです。僕の作品の変遷を意味すると同時に、すべての作品をつなぐものでもありますね。

─今回は、展覧会に加え、それに合わせて構成したライブパフォーマンスが会期直前の週末に行われます。いわゆる音楽のライブイベントを展示空間で行うことについて、どのように考えていますか?
日本には僕が尊敬する本当に素晴らしいアーティストがいっぱいいて、一緒に仕事をしたいな、といつも思っているんです。だから、日本で展覧会をするのって、絶好の機会だったんです。¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$Uは、2019年に北京のMWOODSで行われた展覧会「TRANCE」でのパフォーマンスで、DJセットの最後の1時間を担当してくれたんですけど、プレイしていたときマジでトランス状態になってたんですよ! BOILER ROOM TOKYOでの彼のプレイって見たことあります? ¥ØU$UK€は、自分の身体やエネルギー、いや自らの全てをDJセットに捧げながら、もう明日死んじゃうかも、というくらいの熱量で、それが最期のプレイみたいにDJするんですよね。初めて彼のプレイを見たときはもう、めちゃくちゃ感動しました。
Mars 89の新作は非常にダークで、ねじれや歪みがたくさんあります。僕はパフォーマンス作品の中にさまざまな種類のレイヤーを作り出そうとしてるんですけど、それと通じるところがあるんです。VMOはリードヴォーカルがとてもキュートでありながら、ブッ飛んだスタイルで強烈なコントラストを生み出すんですけど、例えば僕の作品で、スーパーKawaiiフィギュアと、歪んだものをぶっつけちゃうのとかに似てるんですよね。Eartakerにはお会いしたことがないんでワクワクしているんですけど、出演をお願いしたすべてのアーティストのパフォーマンスは、どこかで僕の作品と関係しているような気がしていて、今回の展覧会全体のムードを盛り上げてくれると思っています。彼らの作品が本当に大好きなんで、僕自身がライブパフォーマンスをすごく楽しみにしています!
-
![]()
Mars89/チェン・ティエンジュオ「牧羊人」ライブ・パフォーマンス(2021年10月3日) -
![]()
VMO/チェン・ティエンジュオ「牧羊人」ライブ・パフォーマンス(2021年10月3日)

2021年10月05日(火)更新
- チェン・ティエンジュオ(Tianzhuo Chen/陈天灼)
- 1985 年北京生まれ。ロンドンのセントラル・セント・マーチンズでグラフィックデザインの学位、チェルシー・カレッジ・オブ・アートでファインアートの修士号を取得。2012年に帰国後は中国で複数の展覧会を開催した。2015年、パリのパレ・ド・トーキョーにて、海外で初めての個展を開催。ヴィジュアルアーツ作品のほか、パフォーマンス作品も制作している。チェンのオブジェクトやパフォーマンス、映像作品は、カラフルでグロテスク、キッチュなイメージを用いてアジアの心霊主義やLGBT、イコノグラフィー、舞踏、ヴォーギングやクラブカルチャーについて直接的に言及し、消費主義や超越主義といったテーマに触れながら我々を取り巻く道徳的態度の崩壊と信念との間を接続する。チェンの作品は、厳密に台本に沿ったストーリーや思考、政治的声明と、現代のクラブ文化やカウンターカルチャーに関わるセルフ・エンパワメントの儀礼化された出来事とを織り交ぜる。
Related Pages
関連ページ