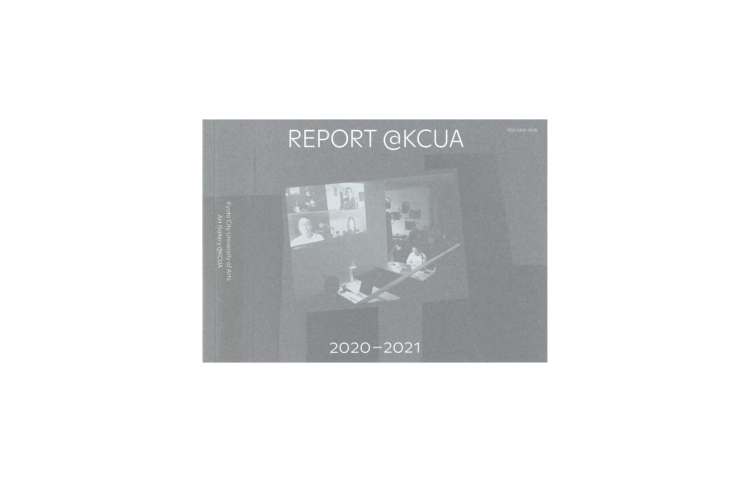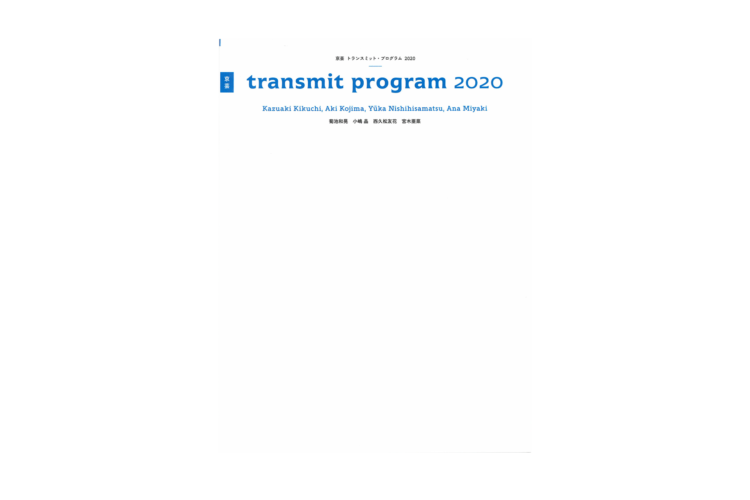INTERVIEW @KCUA
「京芸 transmit program 2020」作家インタビュー(2)
小嶋 晶
聞き手:岸本光大(京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA 学芸員)


「京芸 transmit program」は京都市立芸術大学卒業・大学院修了3年以内の若手作家の中から、いま、@KCUAが一番注目するアーティストを紹介するプロジェクトです。アーティストの活動場所として日本でも1、2を争う都市京都における、期待の新星を紹介するシリーズとして、毎年春に開催しています。
「京芸 transmit program 2020」カタログ(近日発売予定)より作家インタビュー部分を公開いたします。第2回は人間の生について、ペインティングを起点としてさまざまなメディアを用い躍動的に表現しようとする小嶋晶(こじま・あき/油画)さんのインタビューです。
作家ステートメント
看護師として働いてきた約十年間、人間の生死と絶えず関わってきた中で生まれた、アニマについての興味や関心が、私の創作の根源的意欲になっている。しかしそれは人智の及ばない対象のため、焦点はいつもぼやけている。そこで、多角的に辺縁をなぞることでその姿を捉えようとしてきた。 私にとって芸術活動とは、物事を捉えるための方法であり、共有するためのツールである。私の捉えた物事と、他者の捉えたそれは同じではないが、どちらも物事の一つの側面である。故に他者との関わりを通して、物事を捉え直していく必要がある。新しく見出した側面を一つの事実として視覚情報に還元する。こうして事実を積み重ねていくことで見えるアニマの姿があると確信している。 今回の展示は、前回に引続いて「生」をテーマにしており、これもアニマの一端としての位置付けになる。 母親と一体であった完全な状態から分離し、個として存在することになった私たちは、その欠損を補完するために外部のもの(友達/恋人/音楽/本などのあらゆるもの)と一時的に一体となることを繰り返す。これを私は生として作品にしてきた。しかし、外部から補完するだけでなく、内部(自分自身)を強化・発展させることによって欠損を補完する生もあるのではないかと考え、インタビューを通して生の在り方を再解釈した。


—《自分になる》では、見た目を変化させることで自己回復 を図ろうとする方を取材の対象にしていますね。
小嶋:自分の内面から湧き上がる衝動を優先して、それを実行することで現状を変えることは、とてつもないエネルギーが要ることですし、並大抵のことでは無いと思います。また個性化の過程で一般的に悪とされるような部分(collective shadow)と統合していくのは現代社会では非常に困難なことだと思います。それでも突き進んだ先に見える景色に非常に興味がありますね。規範に縛られず、自分がなりたい自分になるべく行動している方を見ると、とても素敵だと思うし憧れます。しかし、身体変工はあくまで一つの手段で、見た目の変化はアクションを起こした結果というか副産物なので、身体を変えることと自分になることは必ずしも結び付いていないと思います。目指す自分の在り方はそれぞれなので。
—絵画専攻を修了されましたが、どのように絵に関わってこられたのでしょうか。
小嶋:小さい頃から絵は好きでよく描いていました。一番身近で手っ取り早くて、誰でも使える表現方法ではあると思っています。油絵はパートとして働きながら通った大阪芸術大学の通信の授業で学びました。なかなか油絵具は使い慣れなかったのですが、デザインの授業でパソコンに向かって描くより、性に合っている感じがしました。大学院で学ぶ前は、自分で作った炭を使って絵を描いていました。自分とは何だろうと考えた時、まず食べ物によって自分の体が形作られていると考えて、自分が食べる筈だったものを焼いて炭にして、それでパネルに寝転んだ自分の体の形をなぞっていました。大学院に入った当初は新しいことがしたかったので絵を描かず、アニマに関する15人分のインタビュー映像と、そこから浮かび上がったアニマに関するオブジェクトを合わせて作品化することに取り組みました。これが消化不良だったのと、絵を描くゼミだったこともあって、また絵に戻りました。卒業制作時には、インタビューを元にした生についての考えを曼荼羅のように図解する作品を作ったのですが、意図が伝わり難いようで、違う方法を考え始めました。絵だけじゃ、自分がしんどいぞと思って。
-
![]()
《bpm60》(2020) -
![]()

—絵・映像・モノで作品が構成され、イメージ伝達のためなら手段は問わないような印象があります。手近なメディアを並列的に捉えようとする、ある種の現代的な感覚によるのかもしれませんが、それらをどのように使い分けていますか。
小嶋:コンセプトをまず考えて、それを表現するのに適したメディアを選択するようにしています。作品の一部が絵である必然性についてよく尋ねられるのですが、自分でもよくわかっていません。描画に対する技術的なコンプレックスを抱いているせいで、他のメディアにも頼っているのかもしれないですね。《bpm60》では母の心臓の絵を描きましたが、もしイメージ通りの映像が作れたのであれば、そちらの方が良かったかもしれないとも思います。でも絵を使わないでやると、どこか物足りなさを感じるような気がします。描いている時の方が充実感を得られます。
2020年7月26日(日)更新
Related Pages
関連ページ