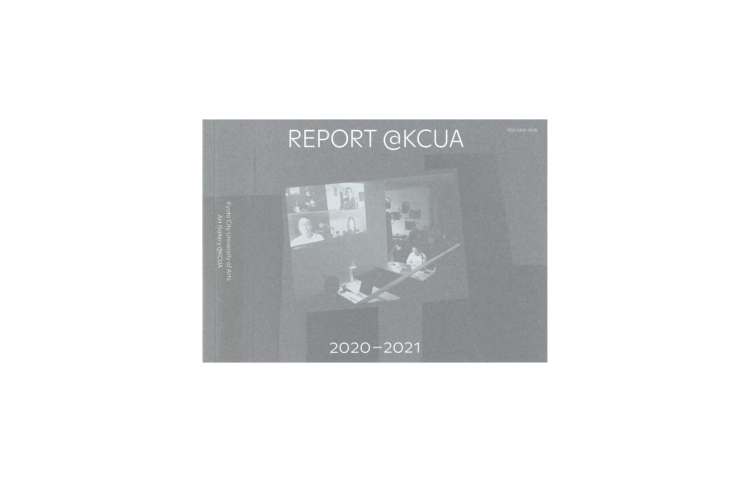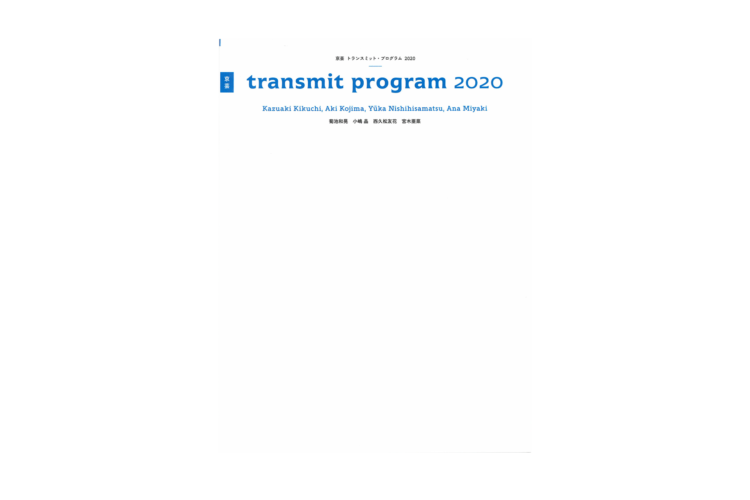INTERVIEW @KCUA
「京芸 transmit program 2020」作家インタビュー(4)
宮木亜菜
聞き手:岸本光大(京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA 学芸員)


「京芸 transmit program」は京都市立芸術大学卒業・大学院修了3年以内の若手作家の中から、いま、@KCUAが一番注目するアーティストを紹介するプロジェクトです。アーティストの活動場所として日本でも1、2を争う都市京都における、期待の新星を紹介するシリーズとして、毎年春に開催しています。
「京芸 transmit program 2020」カタログ(近日発売予定)より作家インタビュー部分を公開いたします。第4回は人の行動がその場の空間、環境などにもたらす変化や現象をパフォーマンスやインスタレーションで表現する宮木亜菜(みやき・あな/彫刻)さんのインタビューです。

作家ステートメント
生活環境における私的要素と公共要素の関係性に重きを置いて制作をしている。特定の地に身を置く際に、周囲の環境や文化、あるいは人との関わりによって、からだと空間は変容する。それらの変化を、物質と身体との関わりによって、インスタレーションやパフォーマンスの形式で提示している。過去の制作では、生活空間そのものを粘土で作り出したり、習慣的行為から部分的な動作を抜き出して行ったパフォーマンスなどがある。
今回の作品では睡眠という行為に着目した。私にとって眠ることは容易いことではない。無抵抗な睡眠は私を不安にし、眠らなければならない時に眠ったふりをさせる。眠ったふりをしている間に眠ってしまうけれど、ものが動き、夜は夢の中で昼へと変わる。大きなカバのとなりで眠っていたこともある。私の夢はいつも昼間で、昼から朝へと目を覚ますから、ここがどこなのかわからなくなる。
睡眠は私的でありながら、意識の外に落ちていくという意味で私的な行為ではありえない。休息のための眠りは私にとっての不安であり、知らされた眠りは、知られていることをどこかで諦めていく。会期中、私を含めた数十人によるパフォーマンスを行う。「10人で同時に眠る」「身体を疲れさせる」「恋人と2人で眠る」「女性の集まり」「位置」「ひかり」「視線」「安心感」「夢への影響」など、日によって参加する人数や性別、ものの位置などが変わっていく、合計18日間のパフォーマンスを会期中の土日祝日に実施する。パフォーマーはいかなる状況の中でもただひたすら“眠る”ことを目的にそれぞれ動く。
—現在のご自身の活動をどのように捉えていますか?
宮木:美術をやっているという意識はあまりなく、心の拠り所として今の活動があると考えています。京都市立芸術大学に入学してからは、美術を学んで制作をすることを当たり前のように思っていました。実際に助けが欲しい時、おのずとその中で救いを求めたという感じです。普通であれば、セラピーなどが心理的に辛い時の頼りになるかと思います。例えばセラピストとの会話の中で、自分の言葉で体験などについて話せるようになることが、克服への道につながるのと同様に、私にとっては美術の活動がその役割を担っているのかもしれません。克服を直接的な目的とはしていないのですが、言葉ではない方法を使って新しい体験をしたり、他者を組み込みながら作品を見てもらうことが、何かと向き合う手段になるのだと思っています。パフォーマンスを通して予想外の発見をすることがありますが、事後的に何かしらのヒントとして重要になることは多いです。


— パフォーマンスで使用される装置をそのまま会場で常に展示していますね。
宮木:行為の痕跡として展示しています。パフォーマンスによって生じたベッドのわずかな窪みや、枕元に落ちている髪の毛1本を手がかりに、そこにはいない人の気配を想像することができます。装置のレイアウトはパフォーマンスの時々に、行為に集中するための配置へと変化します。目を閉じた状態で感じる周りの光量や色、目を開いた時に映る情報、布団の肌触りなどに気を配りながら、心地の良いものと悪いものを取り入れて配置を決めます。装置を見ることから作品全体を想像してもらうのも良いし、造形的に構成されたものなのかなとか、自由に見てもらえたら嬉しいです。「どう見たら良いか」と尋ねられることがありますが、こちらが感じていることと、見る人が感じることがぴったり合わさってはいけないとも思っています。むしろ色々な見方へ広く展開できる方法について考えています。鑑賞者の個人のことに少しでも紐づくことがあればと思います。

—新型コロナウイルスの影響でパフォーマンスの内容が変更・一部中止となりましたが、どのように受け止めていますか。
宮木:コロナウイルスに初期の予定を邪魔されてしまったという気持ちはありますが、ネガティブには捉えていません。むしろ作品と世の中の状況との間につながりが生まれることになったと思っています。私は物心がついてからの入院の経験の記憶はないのですが、展示しているベッドと病床のイメージが結びつくことで、誰とも面会できずに病室で数週間を過ごさなければならない状態を想像し、堪え難いであろう恐ろしさを覚えました。そもそもパフォーマンスには偶然性がつきもので、それは重要な要素の一つだと思っています。その場やその時に偶発的に発生したことをリアルタイムで素材の一つへ置き換えて、作品を展開させていく感覚でもあります。近いうちに、計画どおりの形で、パフォーマンスを実行したいと思っています。私以外の人を作品に加える初めての試みです。そこで浮かび上がった何かが次の展開へ繋がっていくかもしれません。
2020年7月26日(日)更新
Related Pages
関連ページ